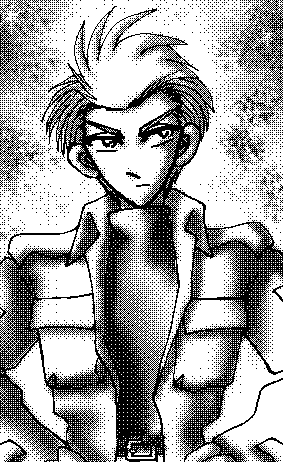揺れる木漏れ日をその褐色の肌に受けて、すらりと背の高い少年が並木通りを歩いている。
今日は珍しく、端正なその顔に不機嫌さがのぞく。
話の発端は昨日にさかのぼる。
イタリアに行くとだけ言い残して姿を消したミハエルが、夜になっても戻らなかった。
行き先は分かりきっていたので、エーリッヒは、いつもの事だと思っていたが、シュミットは気が気ではない。
シュミットにとっては、その行き先が大問題なのだ。
不意に電話のベルが鳴って、シュミットは慌てて受話器を取る。
受話器の向こうからは、いつも通りの のんびりした声。
「あのね、カルロのところにいるんだ!今日は泊めてもらう事になったから・・・わぁ」
ミハエルの声が突然遮られた。
続いて聞こえてきたのは、シュミットにとっては身の毛もよだつ不愉快な声。
「電話代だってバカになんね―んだぞ!ったく、いちいち お供の二人に電話することねーだろ」
「カルロ!貴様、ミハエルに何かしたら承知しないぞ!!」
シュミットは受話器に噛み付くような勢いで怒鳴るが、相手が遠く離れたイタリアでは手も足も出ない。
やきもきするシュミットをあざ笑うように、カルロは言葉を返す。
「さーてねぇ・・・何か、やらかしちまうかもよ?」
耳障りな音を立てて、電話が無造作に切られた。
そーっと その場を去ろうとするエーリッヒの背中に、シュミットの怒鳴り声が突き刺さった。
「明日の朝一番でイタリアに向かうぞっ!」
そういった訳でエーリッヒはイタリアにいるわけだが、イタリア行きを切り出した人物の姿がない。
今日は、アイゼンヴォルフの研究所で、定例の会議が行われる日だった。
リーダーが不在な以上、ナンバー2であるシュミットが出席せざるを得ない。
というか、ミハエルがいてもいなくても、会議に出席するのは、いつもシュミットなのだ。
ミハエルを迎えに行くついでに、シュミットと二人きりでローマのデートを楽しもうと考えていたエーリッヒは、まるで的が外れてしまった。
彼が珍しく不機嫌な原因は、シュミットが自分の隣にいない事に他ならない。
エーリッヒはふっと息をつくと、新緑の眩しい木々を見上げた。
何だかんだ言っても結局、自分がシュミットの頼みを断るはずが無い。
他ならぬシュミットだから。
彼にとっては女神のような その美しい顔を思い浮かべると、不機嫌な気分も晴れた。
エーリッヒは、カルロの住むスラム街へと歩みを進めた。