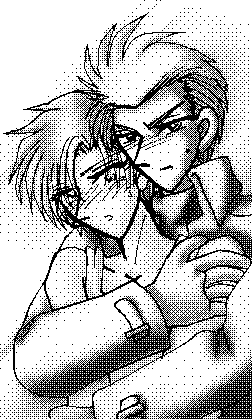エーリッヒはきっと、とても優しい目で私を見てくれる。
でも・・・私は、エーリッヒに優しくされる資格など、無い。
「・・・私は、勝手な人間だ」
エーリッヒでなければ、耐えきれずに離れていくだろう。
ワガママで自分勝手で気が短くて・・・自分でもうんざりするくらい、嫌な人間。
エーリッヒでなければ、いや、エーリッヒだって、いつかは私に愛想を尽かせて去っていくのではないか・・・?
シュミットは気が付いていない。
エーリッヒがシュミットの傍にいるのは、離れていかないのは、彼が優しすぎるからでも、幼なじみの腐れ縁だからでもない。
シュミットが本当に、自身が思っているような人間なら、エーリッヒは傍にいたりはしない。
エーリッヒは何も言わずに、シュミットの背中を見つめている。
微かに震える、白く しなやかな肩。
自分よりずっと華奢で、頼りないその肩は、時に自分よりも ずっと力強く見えることがある。
けれど、時に自分より何倍も重い荷物を背負って、今にも壊れてしまいそうに見えることもある。
「お前には、感謝してるよ・・・いつも、私のワガママに付き合わせて・・・メーワクばかり、かけ・・・」
エーリッヒはシュミットに駆け寄ると、その体を 力いっぱい抱きしめた。
最初、何が起きたか分からずにいたシュミットは、自分がエーリッヒの腕の中にいることに気づくと赤面した。
「な、何だエーリッヒ!・・・離せっ」
慌てて離れようとするが、後ろから回された腕は少しも緩む気配が無い。
「シュミット・・・」
穏やかな低い声。
耳に心地よい その声で名を呼ばれると、途端に力が抜けてしまう。
シュミットは観念して、大人しくエーリッヒに体を預けた。
「・・・俺は、お前の事をメーワクに思ったことは一度も無い」
「お前が誰より責任感が強くて、誰よりチームの事を一生懸命考えているか、俺は、知ってるから・・・!」
エーリッヒは、俯いているシュミットの髪と頬に唇をかすらせると、冷たくなった白い肩を、その手で包んだ。
「・・・・・ありがとう、エーリ・・・」
シュミットはエーリッヒのシャツの袖を探るようにして掴むと、小さな声でつぶやいた。