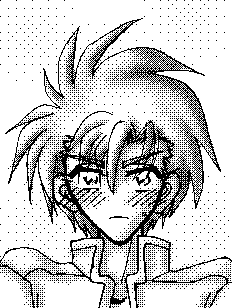さっきまで、あんなに熱かった頬も、早かった鼓動も、
まるで嵐が過ぎ去った後の海のように、穏やかだった。
「どうして・・・リオンはしないの?」
リオンは驚いたように顔を上げた。
深いマリンブルーの瞳で見つめられても、今度は顔をそむけることはなく、烈は真っ直ぐに見つめ返す。
「リオン・・・してくれたこと無いよね、どうして?」
「僕には・・・したくないの?」
烈の瞳が揺れて、リオンの胸が痛んだ。
強いとばかり思われている この少年の、普段は隠された繊細で柔らかな心に触れる瞬間。
きっと、今日に始まったのではないであろう烈の不安に気がつかなかった自分に怒りを感じる。
「したくないわけ無いだろ!俺は烈にキスしたいよ!!」
切羽詰って、思わず声に力が入ってしまった。
目を丸くした烈がポンと顔を赤くして、直後、まるで連鎖反応のようにリオンも赤面する。
「あ・・・いや・・・」
リオンは、あたふたしてバンダナとスコープを外した。
同じ習慣を持っているとはいえ、ブレットと違って奥手で照れ屋なリオン。
けれど、リオンが烈に、たとえ頬にでもキスをしないのは、性格のためだけではない。
「その・・・烈は そういうの、苦手かなって思って・・・嫌われたくなくて・・・それで・・・」
安堵感に包まれ、自然と笑みがこぼれる。
不安が消えて、曇り空のような心が晴れたとき、烈はもう一つ自分が持っていた気持ちに気が付いた。
「ね、リオン・・・したかったら、我慢しなくていいよ」
「嫌ったりしないよ、僕、きっとリオンなら・・・嬉しいと思うから」
そう言って微笑みかけられた幸せな少年は、手にしていたスコープをポトリと絨毯の上に落とした。